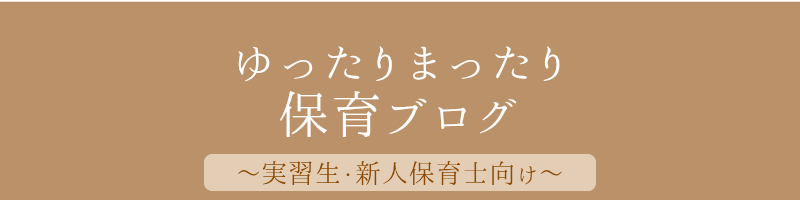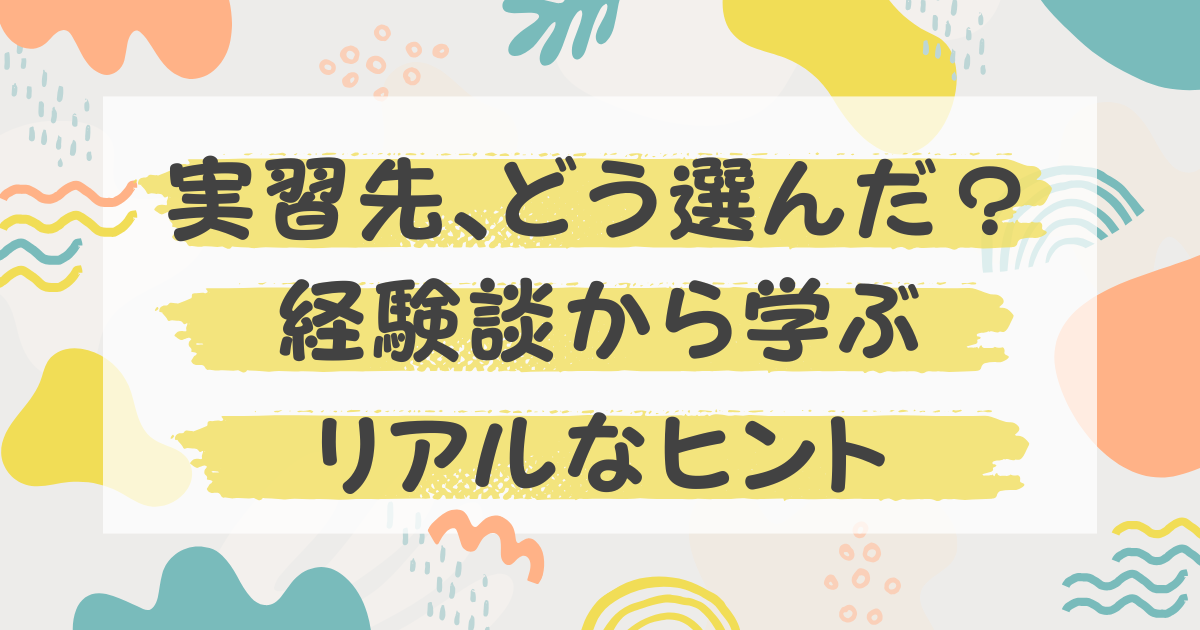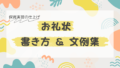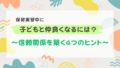「実習先の保育園ってどうやって決めるの?」「地元か、今住んでいる場所の近くか、どっちにしたらいいの?」「私立と公立って何が違うの?」
学生時代、そんな疑問に悩んだ私が、実際に保育園・幼稚園・施設での実習を経験し、気づいたことや選び方のポイントをまとめました。実習先選びに迷っている保育学生さんの参考になれば嬉しいです。
※ちなみに私は四年制大学で「保育士資格」「幼稚園教諭第一種免許」を取得しました。この記事の内容は、平成21~22年(2009~2010年)当時の経験をもとにしています。
実習で訪れた園・施設一覧
| 実習順 | 種類 | 園名(概要) | 特徴・学びのポイント |
| 1 | 幼稚園 | 大学付属 | グループ実習、責任実習あり、添削厳しめ |
| 2 | 保育園 | 母園(徒歩圏) | 全年齢クラス体験、設定保育5本、懐かしさあり |
| 3 | 保育園 | 地元(バス通勤) | クールな雰囲気、大手組織、丁寧な日誌指導 |
| 4 | 児童養護施設 | 地元 | 泊まり込み、全世代の子どもと関わる、実習生同士で助け合い |
| 5 | 幼稚園 | 地元(自由保育) | 縦割り、自由保育、自然豊か、先生の保育技術の高さ、日誌が書きやすかった |
実習先を選んだ理由と感想・学び
1. 幼稚園(大学付属)
選んだ理由
- 大学付属園のため、必修で行かなければならなかった
実習の内容・特徴
- グループ実習、年長クラスを担当
- 責任実習(1日の保育をグループで実施)あり
- 部分実習(手遊び、絵本の読み聞かせ)あり
- 実習前に準備物(製作、掃除など)も多く指導細かめ
- 子どもたちは実習生慣れしている
- 日誌の添削が非常に厳しい
感想・学び
- 初めての実習で緊張の連続だった
- 同年代の若い先生が非常にしっかりしていて、焦りを感じた
- 日誌がとにかく苦痛。寝不足で仕上げることが大変。厳しい添削に落ち込みそうになった
- 部分実習の絵本読み聞かせが楽しく、子どもたちの反応に嬉しくなった
- 手遊びの内容をその場でアレンジし、臨機応変に対応できたことを褒められた
- 遊びの中で自然に歌を取り入れる先生の姿に感動
- 製作で細かい注意が多く、「そこまで完璧にしなくても…」と当時は思っていた
2. 保育園(母園)
選んだ理由
- 幼少期に通っていた園で、知っている先生もいて行きやすかった
- 実家から徒歩圏内で通いやすい
- 母園の懐かしさを味わいたかった
実習の内容・特徴
- 2日ずつ各年齢クラスに入り、計5回設定保育を実施
- シフト制勤務(早番・遅番あり)を経験
- 園全体はのびのびした雰囲気だったが、担任の先生によって保育のやり方に差あり
感想・学び
- 知っている先生が多く快く受け入れてくれたが、やはり緊張した
- 設定保育5回は指導案作成と準備が大変だったが、子どもの前に立つ経験を積めて自信になった
- 就職後もこの時の設定保育の経験が活かされた
- 絵本の読み聞かせを褒められ、「私も見習いたい」と言われたことが嬉しかった
- 絵画指導で子どもたちの絵がほぼ同じになっていて違和感を覚えた
- 就職も少し考えたが、保育観の違いや「母園は思い出の場所にしておきたい」という思いから見送った
3. 保育園(地元の保育園)
選んだ理由
- 実家からバス通勤可能な距離
- ホームページの雰囲気と直感で選んだ
- 第1希望の園が電話で断られたため
実習の内容・特徴
- シフト制勤務
- 全クラスに2日ずつ入り、2歳児クラスで設定保育
- 日誌の指導が丁寧
- 園の雰囲気は落ち着いていてクールな印象
- 後に大手法人の保育園だったことが判明(研修・マニュアルが充実)
感想・学び
- 日誌の書き方を丁寧に教えてもらえたが、当時はうまく理解できず苦労した
- 後から「あの時の指導がありがたかった」と実感できた
- 「もっと積極的に動かなきゃ」と思っていたが、反省会で評価されたことに驚き嬉しかった
- クールな印象だったが子どもが落ち着いて過ごせていて、「元気で明るい先生」じゃなくてもいいんだと学んだ
- 遊具で遊んでいる子どもがいて「そばで見ていないと危ないでしょ!」と注意された時はびっくりしたが、危機管理意識を持つきっかけに
- 理想の保育とは少し違い、就職希望には至らなかった
4. 児童養護施設
選んだ理由
- 大学の実習先一覧から選択
- 地元で通いやすく、先輩から良い施設だったと聞いた
- 乳児院と迷ったが、児童養護施設にも興味があったため選択
実習の内容・特徴
- 泊まり込みのグループ実習(途中の土日は帰宅)
- 幼児から高校生までのクラスをすべて体験
感想・学び
- 特に中高生とは距離があり、打ち解けるのは難しかったが、割り切って施設を理解することに集中
- グループで励まし合えたことで、日誌がスムーズに書けた
- 先生方は頼もしく、子どもとの信頼関係が見えて安心感があった
- 「子どもの前でメモを取らないで」と怒られたことで、メモの取り方・配慮について学んだ
- 大きな声で叱られたことはショックだった。私に後輩ができたら「冷静に伝える」姿勢を大事にしようと思った
5. 幼稚園(地元・自由保育)
選んだ理由
- 自由保育に興味があり、見てみたかった
- あまり聞いたことのない「○○教」の園で不安はあったが、保育内容に惹かれた
- 実家から遠く通勤が大変そうだったが、それでも見たい園だった
実習の内容・特徴
- 縦割り保育・自由保育(毎日同じクラスに入る)
- 先生は私服、スカートを履いている先生もいて驚いた
- 先生は「○○さん」と呼ばれる
- キャラクターのものは禁止
- 木のおもちゃやコーナー保育が整っている
- 園庭が広く、自然豊かな環境
- 絵本『めっきらもっきらどおんどん』をテーマにした環境づくりを展開
感想・学び
- 子どもたちが自ら片付けや集まりに移行していく姿に感動した
- 「自由保育」はただの放任ではなく、計算された環境構成と保育者の意図があることを学んだ
- 絵本『めっきらもっきらどおんどん』をテーマにした環境づくりを展開していたことに私自身もワクワクして感動した
- 「絵本は抑揚を抑えめに読む」という考え方に驚いたが、子どもの想像力を育むためという理由で納得した
- 人形の顔が描かれていないのは、子どもが自由に想像できるためと知って学びになった
- 実習中、気づきが多く日誌がスムーズに書けた
- 通勤は遠かったが、実習が充実していたため苦にならず、むしろ就職したいと感じた(最終的には乳児保育をしたくて保育園に就職)
- 今の自分の保育観を築いた、原点となる実習だった
今だったらこう選ぶ!保育実習先の選び方6つのポイント
「実習先って、どうやって決めればいいんだろう…?」
そんな悩みを持つ保育学生さんへ。
実習先の選び方に“正解”はありませんが、いくつかのポイントを押さえておくと、自分に合った園に出会いやすくなります。
今回は、私自身の実習経験をふまえて、「今の私だったらこう選ぶ!」という視点で、実習先選びのコツをお伝えします。
① 保育の特色がはっきりしている園を選ぶ
保育の方針やスタイルは、園によって実にさまざま。自分が学びたい内容が明確になっていると、実習の学びもぐっと深まります。
まずは、主な保育の方針を一覧で見てみましょう。
| 保育の種類 | 特徴 |
| モンテッソーリ教育 | 「自立」と「自己選択」を大切に。子どもが自ら選んだ活動に集中できる環境。独特な教具を使い、感覚・言語・数などを育てる。 |
| ヨコミネ式教育法 | 読み書き計算、体操などを日常的に取り入れ「できる喜び」を育てる。競争心や達成感も重視。 |
| 自由保育 | 子どもが好きな遊びを選ぶスタイル。主体性を育む。保育者は見守りが中心。 |
| 一斉保育 | クラス全員で同じ活動をする。集団行動のルールや協調性が育ちやすい。 |
| 音楽保育(リトミックなど) | 音楽を通じて表現力・リズム感を育てる。楽器や歌が好きな人におすすめ。 |
| 食育に力を入れる園 | クッキング保育や野菜の栽培を通して、食べ物への感謝や栄養への関心を育てる。 |
| 自然保育(森のようちえん) | 自然の中で遊びながら、五感や身体を育てる。泥んこ遊びも大歓迎。 |
| 縦割り保育 | 異年齢の子どもが同じクラスで生活。年下を思いやり、年上から学ぶ関係性が育つ。 |
| 担当制保育 | 一人の保育者が少人数の子を担当し、信頼関係を大切にした保育。特に乳児期に効果的。 |
| プロジェクト保育 | 子どもの興味を出発点に、探究的な学びを展開。テーマを深めていくスタイル。 |
| 異文化・多言語保育 | 英語や他言語を日常的に取り入れた保育。インターナショナル系の園で多い。 |
どんな保育に興味があるかを考えながら、「この園なら自分の学びたいことが得られそう」と思える園を探してみてください。
② 園の雰囲気が伝わる情報をチェック!
最近では、Instagramやブログを運営している園も増えています。
子どもたちの日々の活動の様子、先生の雰囲気、園内の様子などが分かるので、必ず目を通してみましょう。
見るべきポイント:
- 子どもたちの表情(楽しそう?自然?)
- 先生の雰囲気(きびしい?優しい?ナチュラル?)
- 活動内容(保育の特色と合っているか?)
③ 保育園の種類や園児数にも注目!
「公立 or 私立」「小規模 or 大規模」などで、保育の雰囲気や運営体制は大きく異なります。
公立と私立の違い
| 公立保育園 | 私立保育園 |
| 公務員保育士が勤務 | 社会福祉法人や学校法人などが運営 |
| マニュアルがしっかりしている | 園ごとに特色がある |
| ベテラン職員が多い | 若い職員が多い傾向も |
| 産休・育休制度が整っている | 園によって福利厚生に差あり |
小規模保育園・中規模保育園・大規模保育園の違い
| 園の規模 | 特徴 |
|---|---|
| 小規模保育園(別制度) | 0〜2歳児が対象(3歳以上は卒園)/定員6〜19名程度。職員数も少なく、家庭的な雰囲気で一人ひとりに丁寧な保育が可能。市町村の独自基準で運営される場合も多い。 |
| 中規模保育園 | 定員60〜90名程度。0〜5歳児までが在籍。職員やクラス数も適度で、全体の雰囲気が把握しやすい。担任間・年齢間の連携が求められる。園によって方針に個性が出やすい。 |
| 大規模保育園(マンモス園) | 定員100〜200名以上。複数担任制が多く、園内ルールや分業が細かい。集団行動や行事が盛ん。職員も多いため、チームワークや報連相が重要。保護者対応や行事の運営も規模が大きい。 |
- 小規模園は、未満児中心の丁寧な関わりを学びたい人におすすめ
- 中規模園は、全体の流れを把握しながらも丁寧な保育や連携を体験できる
- 大規模園は、行事の規模・職員の多さなど「園運営のリアル」が見られる貴重な場
私自身は小〜中規模の園で実習をしましたが、今思えば一度は“マンモス園”(定員200人以上)も経験してみたかったと思います。
④ 場所も大事!生活とのバランスを考えて
実習期間は朝も早く、体力も気力も使います。
なるべく「通いやすさ」や「生活スタイル」に合った場所を選ぶのがベター。
また、園の“地域柄”によって保育の雰囲気や保護者の関わり方が異なる場合もあります。
今後の就職活動にもつながる視点として、地域を見るのもおすすめです。
⑤ 口コミもチェック。ただし鵜呑みにしない!
Googleマップや保育園情報サイトなどで、保護者目線の口コミをチェックするのも一つの手です。
例:「園庭が狭い」と書かれていたが、実際には室内あそびの工夫がされていて過ごしやすかった!など。
ただし、保育士としての視点と保護者の感じ方は違うこともあるので、参考程度にとどめておきましょう。
⑥ 最後は“直感”も大切に!
「なんとなくここが気になるな」
「この園のブログ、好きな雰囲気かも」
そんな“ピンときた感覚”も、選ぶうえで大切なヒントです。
実際に行ってみないと分からないことがたくさんあります。迷ったら、自分の直感を信じてみてください。
実習先が「合わないかも」と思ったときこそ、学びのチャンス!
「ここ、なんだか合わないかも…」「先生が怖くて萎縮してしまう」「理想と違ってモヤモヤする」
——そんなふうに感じること、実習では意外と“あるある”です。
でも、どんな園であっても、“学びに変える視点”を持てば、実習は必ずあなたの糧になります。
ここでは、実習を前向きな経験に変えるための3つの視点を紹介します。
① 小さな「良いとこ探し」でポジティブ変換!
自分に合わない園でも、よく見ると「いいな」と思えることがきっとあります。
些細なことでも構いません。意識的に“良いところ”を探してみましょう。
例:
- 先生がテキパキ動いていて、信頼されている
- 掃除が行き届いていて、清潔感がある
- 保護者にいつも笑顔で対応している
② ネガティブな出来事は「反面教師」にする
「こんな言い方されたくなかった」「もっとこうしてほしかった」——そんな気持ちも立派な学びです。
将来、自分が保育者になったときに“どうありたいか”を考えるきっかけになります。
例:
- 子どもへの言葉かけが厳しすぎる → 自分はもっと肯定的な声かけを意識したい
- 指導が怖かった → 後輩には優しく丁寧に伝えるようにしたい
- 園の雰囲気がピリピリしている → 明るくあたたかい保育環境をつくりたい
③「当たり前を疑う」ことこそ、最大の学び
「これは本当に正しいやり方なのか?」
「この園のやり方がすべてじゃないのかも」
そうやって保育の“常識”を疑うことは、実はとても大事な学びの姿勢です。
- 「こんな保育、理想的だな」と思ったら → その背景や理由も考えてみる
- 「この保育はちょっと違うな」と思ったら → 他にどんな方法があるか調べてみる
- 自分の「思い込み」や「固定観念」に気づけることも大きな成長です
この視点は、就職後も大切にしてほしい保育観です。
まとめ|ポイントを押さえて、自分に合った実習先を選ぼう!
実習先選びに“正解”はありません。でも、自分の学びたいことや興味のある保育を明確にしておくと、選択肢がぐっと絞れて選びやすくなります。
迷う時間も、きっと自分と向き合う大切なステップです。
「なんとなく、ここ気になるな」と思える園に出会えたら、それがもう第一歩かもしれません。
どんな園でも、実習で得た経験は必ずあなたの糧になります。
たとえ大変なことがあっても、「よく頑張ったね」と自分をねぎらってあげてくださいね。
あなたの実習が、実りある時間になりますように。
心から応援しています!