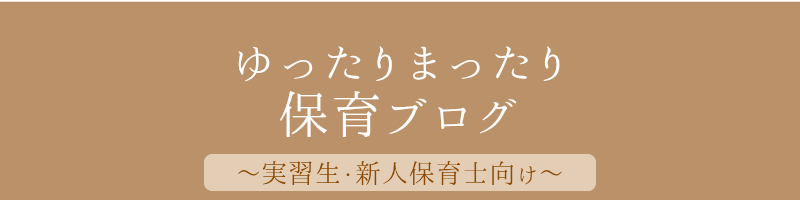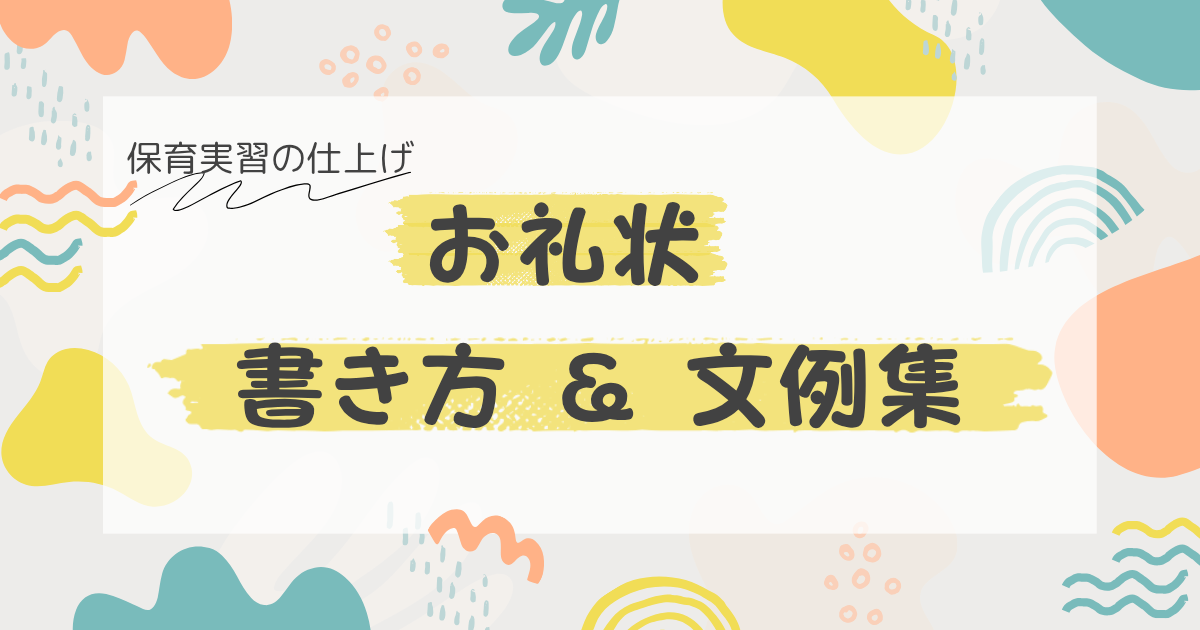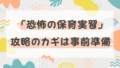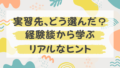「やっと終わった保育実習!」と一息つくのはまだ早いかもしれません。
最後の仕上げとして、「お礼状」の送付を忘れてはいませんか?
この記事では、お礼状の基本的な書き方からポイント、具体的な文例まで詳しく解説します。
- お礼状の形式ってどうすればいいの?
- 前文・主文・末文ってどんな内容を書くの?
- 時候の挨拶「○○の候」は必ず使うべき?
- 封筒の宛名書きのマナーとは?
これらの疑問にお答えし、感謝の気持ちが伝わるお礼状が書けるようになるヒントをお届けします。
文例も多数掲載しているので、参考にしながら「これだ!」と思う表現を見つけてくださいね。
用意する物
以下は、お礼状を書く際に必要な準備物です。それぞれの選び方に注意して揃えましょう。
便箋
派手な柄は避け、白無地や淡い色合いのシンプルなものを選びましょう。文房具店や100円ショップで手に入ります。
封筒
便箋と統一感のある封筒を選ぶことが重要です。便箋とセットで販売されていることが多いので、一緒に購入すると便利です。
- 色・種類:無地の白い封筒を使用します。柄や郵便番号欄のないものが望ましいです。
- サイズ:長形3号(便箋を三つ折りにして入るサイズ)が適切です。
- 縦書き:日本の正式な手紙では縦書きが一般的です。
ペン(黒のボールペン)
にじみにくい油性ボールペンがおすすめです。初心者の方でも扱いやすく、文字が綺麗に見えます。使い慣れたペンがあれば、それを使用するのも良いでしょう。
下書き用の紙
いきなり便箋に書き始めると、失敗することがあります。まずは下書き用の紙を用意し、文章を練り直してから清書するようにしましょう。
切手
事前に封筒のサイズに合った切手を用意しましょう。(郵便局に直接持ち込む場合は不要です。)
その他
定規(文字を揃えやすくするため)や消しゴムなど。
注意:必ず予備の用意を!
書き間違えた場合、修正テープを使わず、新しい便箋に書き直すのが基本です。そのため、便箋と封筒は予備を多めに用意しておきましょう。
また、ペンのインクが少なくなると文字がかすれてしまい、印象が良くありません。予備のペンを用意しておくと安心です。
お礼状を書くポイント
お礼状を書く際は、以下のポイントを意識して書き進めましょう。これらのポイントを守ることで、読み手に誠実さと感謝の気持ちをより確実に伝えられます。
丁寧な敬語を使用する
お礼状では、誤解を避けるためにも正しい敬語を使いましょう。「させていただきます」「お世話になりました」など、基本的な表現が適しています。
感謝の具体的なエピソードを入れる
実習での具体的なエピソード(例:教えていただいたこと、励ましてもらったこと)を盛り込むと、感謝の気持ちが伝わりやすくなります。
季節や状況に応じた挨拶を取り入れる
「寒さが厳しくなってまいりましたが…」など、季節の挨拶を冒頭に添えることで、より丁寧な印象を与えます。
基本の型に当てはめて書く
お礼状には定型の構成(頭語→挨拶→感謝→締めの挨拶→結語)があります。この型に沿うと、失礼のない文面になります。
間違えた場合は修正液を使わず、新しい便箋や封筒に書き直す
お礼状は手書きの場合が多いですが、誤字があれば必ず書き直しましょう。修正液の使用は避けるのがマナーです。
心を込めて丁寧に書く
私は字が汚いことがコンプレックスなのですが、心を込めて丁寧にゆっくり書くことで相手に気持ちが伝わると思っています。決して適当な走り書きになってはいけません。
お礼状の基本構成
手紙には基本の型があります。以下の構成に沿って書けば失敗しません。
- 前文:「拝啓+時候の挨拶+相手への気遣い」
- 主文:「感謝の言葉+具体的なエピソード」
- 末文:「結びの言葉+園の発展を祈る言葉+敬具」
- 後付け : 日付+差出人名+相手の名
それぞれの役割について簡単に解説します。
1. 前文 ∶ 拝啓+時候の挨拶+相手への気遣い
前文は手紙の冒頭にあたる部分です。「拝啓」と頭語で始まり、時候の挨拶と相手への気遣いを添えます。
例)「拝啓(頭語) 桜が満開を迎え、春の訪れを感じる季節となりました。(時候の挨拶) 貴園の皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。 (相手への気遣い)」
2. 主文 ∶ 感謝の言葉+具体的なエピソード
感謝を伝える中心部分です。実習で学んだことや印象的なエピソードを具体的に書きます。
例)「この度は保育実習の機会をいただき、誠にありがとうございました。(感謝の言葉) 実習中は、○○先生のご指導のもと、子どもたちとの関わり方や保育の基本を学ぶことができました。特に○○(エピソード)は私にとって忘れられない経験となりました。(具体的なエピソード)」
3. 末文 ∶ 結びの言葉+園の発展を祈る言葉+敬具
最後に感謝の締めくくりや園の発展を祈る言葉を添えて、敬語で結びます。
例)「貴園での学びを大切にし、今後も努力を続けてまいります。 (結びの言葉)貴園のますますのご発展と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。 (園の発展を祈る言葉)敬具 (結語)」
4. 後付け:日付+差出人名+相手の名
- 日付:本文よりも少し下げて漢字で書きます。
- 差出人名:縦書きなら、行の一番下のほうに。
- 相手の名:本文の高さと合わせます。
「拝啓」と「敬具」はセットで使う
「拝啓」で始めた場合、文末は必ず「敬具」で結びます。これは正式な手紙の形式で、頭語と結語が対応することで文章全体が整います。
他の表現もありますが、公式な手紙には「拝啓」と「敬具」が最適です。
時候の挨拶の選び方|「〇〇の候」と文章形式の違い
時候の挨拶には「〇〇の候」のような形式的なものと、具体的な文章形式の2種類があります。それぞれの特徴を押さえて使い分けましょう。
1.「〇〇の候」の特徴
特徴:簡潔で形式的。主にビジネス文書や公式な手紙に適用。
メリット:無難で誰にでも使える。
デメリット:堅苦しく温かみに欠ける印象がある。
例:「陽春の候、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
2. 文章形式の特徴
特徴:具体的な情景を交えた親しみのある表現。
メリット:温かみや個性を伝えられる。
デメリット:フォーマルな印象が弱くなる場合がある。
例:「桜が満開を迎え、春の暖かさを感じる季節となりました。」
3. 保育実習のお礼状におすすめのスタイル
保育現場では温かみのあるコミュニケーションが大切です。実習先の雰囲気に合わせ、フォーマルな「〇〇の候」と親しみのある文章形式を使い分けましょう。
文例集
ここでは、以下の項目ごとに文例を豊富に紹介しています。
- 前文
- 主文
- 末文
- 全体の文
この中から、自分の感覚にしっくりくるものや、自分の気持ちに最も近い表現を見つけてください。「素敵な言葉だな」と感じたものを積極的に選ぶことで、より自分らしいお礼状が作れます。
前文の文例
季節に応じた前文の挨拶例を以下にまとめました。これを参考に、手紙の冒頭を華やかに彩りましょう。
【春(3~5月)】
- 桜の花が見頃を迎え、春の暖かさを感じる季節となりました。貴園の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
- 木々の新芽が芽吹き、春の息吹を感じる頃となりました。貴園の皆様にはご健勝のことと存じます。
- 桜が咲き誇る美しい季節となり、新たな門出を迎える時期となりました。貴園の皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます
【夏(6~8月)】
- 梅雨が明け、夏の日差しが厳しくなってまいりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。
- 夏の日差しが日ごとに強さを増すこの頃、貴園の皆様にはお健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。
【秋(9~11月)】
- 木々が色づき、秋の深まりを感じる季節となりました。貴園の皆様にはお変わりなくご健勝のことと存じます。
- 実りの秋を迎え、紅葉が美しく色づく頃となりました。皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。
【冬(12~2月)】
- 寒さが厳しくなるこの頃、貴園の皆様にはますますご健勝のこととお祈り申し上げます。
- 新春の候、貴園の皆様にはご清祥のこととお喜び申し上げます。
主文(エピソード)の文例
感謝の具体的なエピソードを伝える主文の例です。自分の実体験に近いものを選び、具体性を持たせましょう。
【例①: 子どもたちとの関わり】
- 子どもたちと日々触れ合う中で、一人ひとりの個性を大切にする貴園の保育方針に感銘を受けました。○○ちゃんが笑顔で○○をしてくれた時、保育のやりがいと喜びを改めて感じました。
【例②: 先生の指導】
- ○○先生には、日々の保育の工夫や子どもたちとの接し方について、丁寧に教えていただきました。特に○○(具体的な指導内容)は、私にとって非常に学びの多いものでした。
【例③: 特別なイベント】
- 実習中に○○行事を経験させていただき、大変貴重な学びとなりました。子どもたちが生き生きと楽しむ姿を間近で見ることで、保育士としての役割の大切さを実感しました。
末文の文例
締めくくりの部分は感謝の気持ちと今後への意欲を伝える場です。
- 貴園で学ばせていただいたことを忘れず、これからの学びに活かしてまいります。今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。
- 貴園の子どもたちの笑顔がこれからも輝き続けますよう、また貴園の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
全体の文例
以下に春・夏・秋・冬それぞれの季節に合わせた全体の文例をまとめました。各文例は保育実習のお礼状としてふさわしい丁寧さと温かみを持たせています。これらを参考に、ご自身の気持ちに合う表現を選んでください。
【春の季節の挨拶】
「拝啓 春暖の候、貴園におかれましては益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。
このたびは、保育実習の機会をいただき、心より感謝申し上げます。桜が満開の園庭で、子どもたちと春探しを楽しむ中で、保育士の仕事の魅力を深く実感いたしました。先生方からご指導いただいたおかげで、保育士として必要な視点や姿勢を学ぶことができましたこと、大変感謝しております。
いただいた学びを胸に、今後も精進してまいります。末筆ながら、貴園のますますのご発展と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。敬具」
【夏の季節の挨拶】
「拝啓 盛夏の候、貴園におかれましてはご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたびは、貴園で保育実習の貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。
水遊びや夏祭りの準備を通じて、子どもたちが笑顔で楽しむ姿を間近で見られたことが、私にとって忘れられない思い出となりました。また、先生方のご指導から、保育士としての柔軟な対応力や、子どもたちへの接し方の工夫を学ぶことができました。
今後も、この経験を糧にさらに努力を重ねてまいります。末筆ながら、貴園のご発展と皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 敬具」
【秋の季節の挨拶】
「拝啓 秋涼の候、貴園におかれましては益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。
このたびは、保育実習の機会をいただき、心より御礼申し上げます。
子どもたちと一緒にどんぐりや松ぼっくり拾いを楽しみながら秋の季節に親しむ活動が、私にとって非常に意義深い経験となりました。また、先生方が子どもたち一人ひとりに寄り添いながら、きめ細やかに保育をされている姿に感銘を受け、自分自身の理想とする保育士像を見出すきっかけとなりました。
今後も、この学びを活かしながら精進してまいります。末筆ながら、貴園の益々のご発展と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。 敬具」
【冬の季節の挨拶】
「拝啓 寒冷の候、貴園の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。
このたびは、保育実習の機会をいただき、誠にありがとうございました。
寒さが厳しい中でも、子どもたちが元気いっぱいに活動する姿に触れ、保育士としての喜びと責任を改めて実感することができました。また、季節に合わせた制作活動や行事の準備を通じて、保育士の細やかな配慮や工夫を学ぶことができましたこと、大変感謝しております。
いただいた貴重な経験を胸に、夢に向かってさらに努力を続けてまいります。末筆ながら、貴園のご発展と皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 敬具」
【オールシーズン使える挨拶】
「拝啓 貴園におかれましては、益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。このたびは、保育実習の機会をいただき、心より感謝申し上げます。
実習期間中、子どもたちの笑顔に触れながら、保育士としての喜びや課題を学ぶことができました。また、先生方からの温かいご指導を通じて、子ども一人ひとりに寄り添う姿勢の大切さを改めて感じることができました。
今後も、いただいた学びを糧に日々精進してまいります。末筆ながら、貴園の益々のご発展と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。敬具」
封筒の宛名書きの書き方
保育実習のお礼状を送る際、封筒の宛名は正しい形式で書くことが大切です。以下の手順とポイントを押さえることで、相手に失礼のない印象を与えられます。
宛名の基本ルール
書く内容
表面:保育園の正式名称、役職(園長)、名前、敬称(様)を記載します。
例:「○○法人 ○○保育園 園長 ○○様」
裏面:自分の住所、学校名、名前を左下に記載します。
敬称の注意点
敬称の重複は避けましょう。「園長先生様」のように「先生」と「様」を同時に使うのは誤りです。
正:○○保育園 園長 ○○様
誤:○○保育園 園長先生様
宛名の書き分け
基本的には園長先生宛てに書きます。ただし、職員全体への感謝を表したい場合は、以下のように書くことも可能です。
「園長先生 職員の皆様」
お礼状の投函の仕方
お礼状を書き終えたら、最後にしっかり投函の準備をしましょう。初心者でも失礼のないよう、以下のステップを参考にしてください。
1. 封筒に正しく宛名を書く
宛名や住所を封筒の中央に丁寧に書きます。相手の名前には「様」を付け忘れないよう注意しましょう。
2. 切手を貼る
封筒のサイズや重さに応じた切手を貼ります。郵便局で確認するのがおすすめです。切手を斜めに貼るのはマナー違反なので注意!
3. 封筒をきれいに封をする
手でしっかり糊付けし、封筒の端が開いていないか確認しましょう。
4.郵便ポスト、または郵便局の窓口から投函
投函の際は、締切時間に間に合うよう余裕を持ってポストに入れましょう。重要な書類の場合、郵便局の窓口から送るとより確実です。
まとめ
この記事では、保育実習後のお礼状の書き方について、必要な準備物や基本構成、季節の挨拶の使い分け、さらに文例を交えながら詳しく解説しました。
この記事を参考にすることで、お礼状を作成する手順が明確になり、自信を持って感謝の気持ちを伝えられるはずです。
ぜひ実習先に心のこもったお礼状を送り、良い印象を残してください!